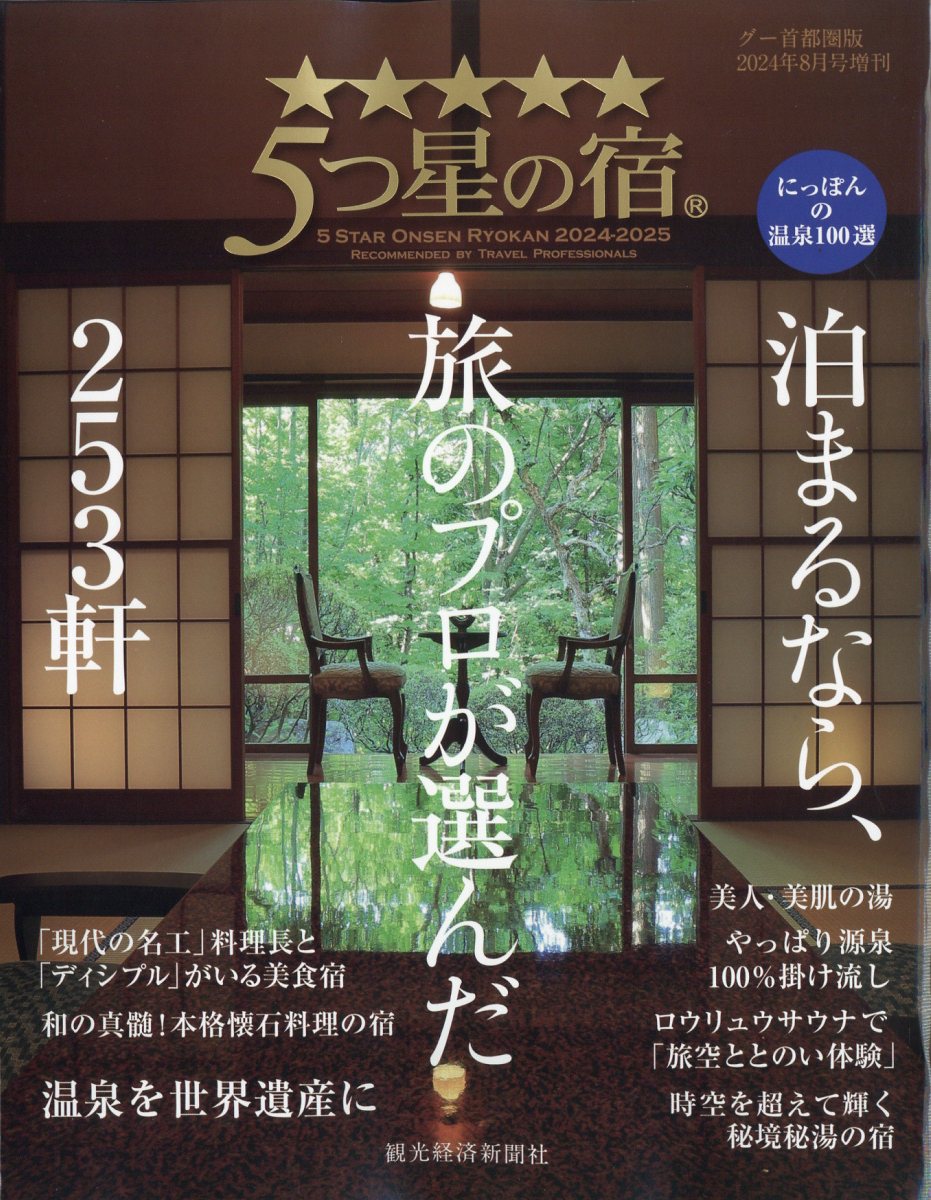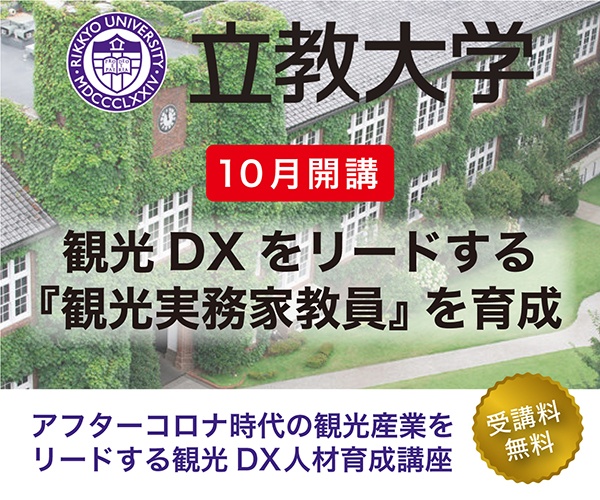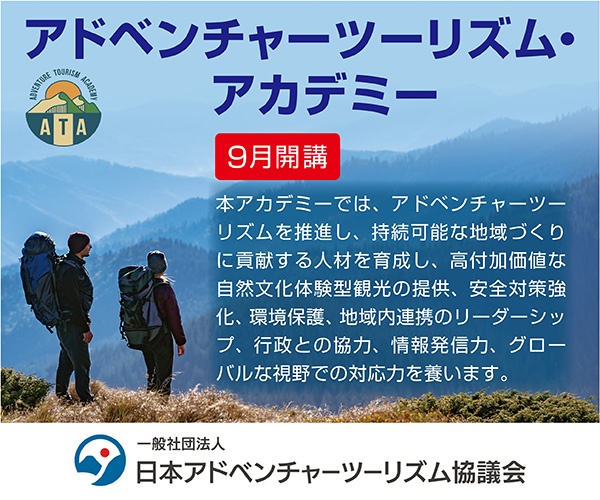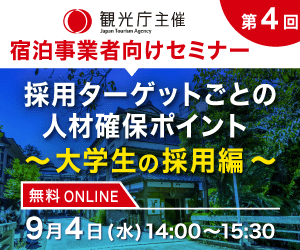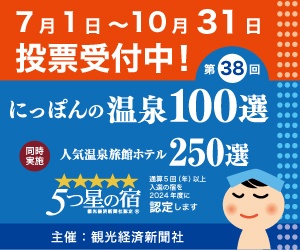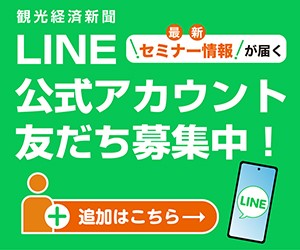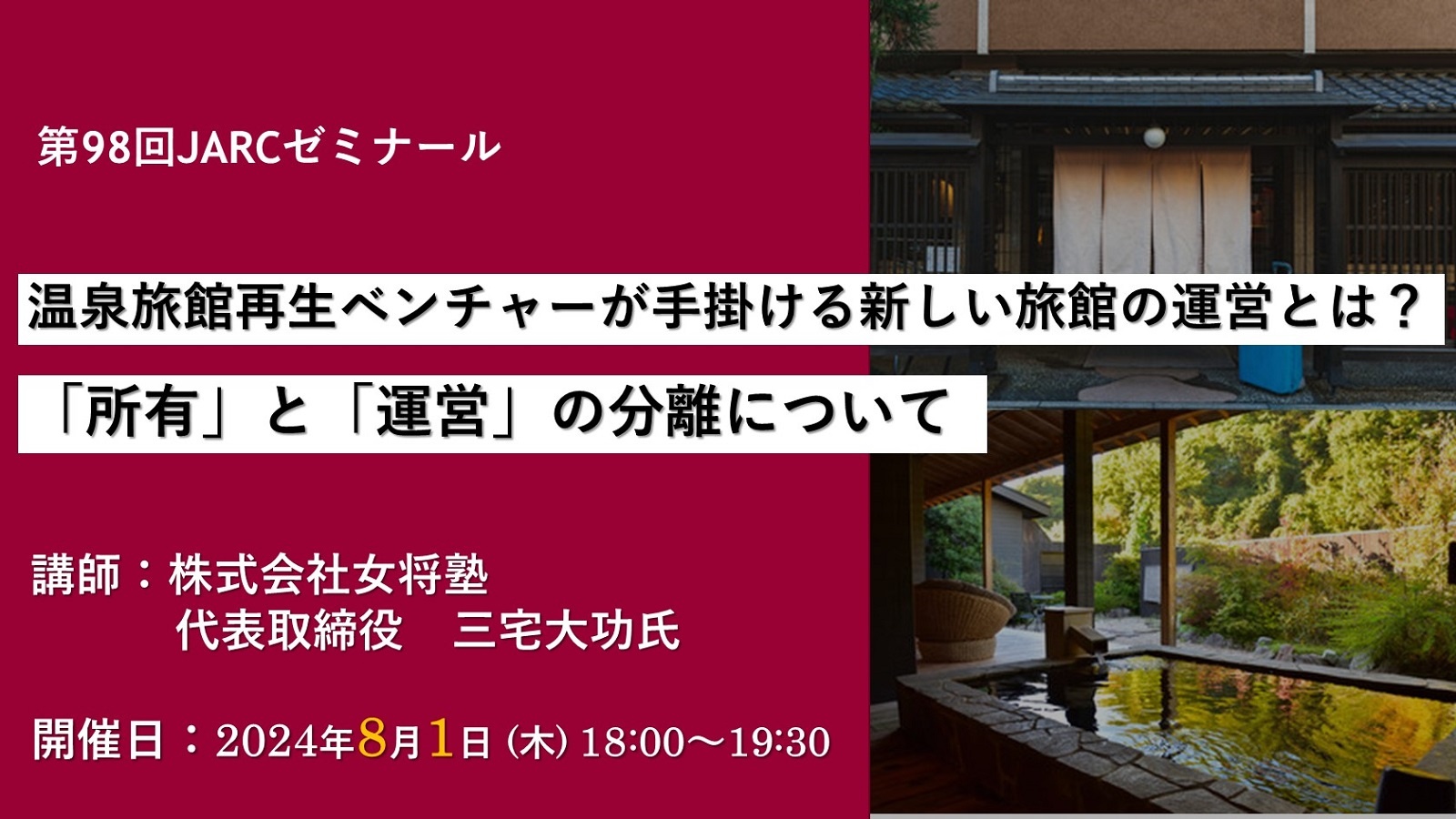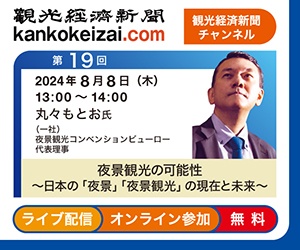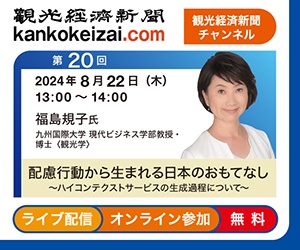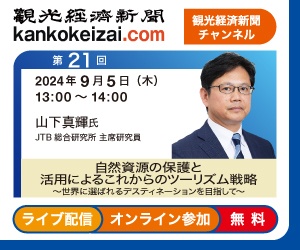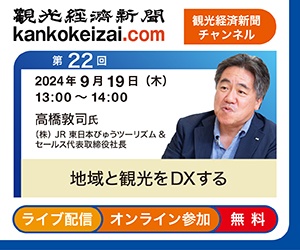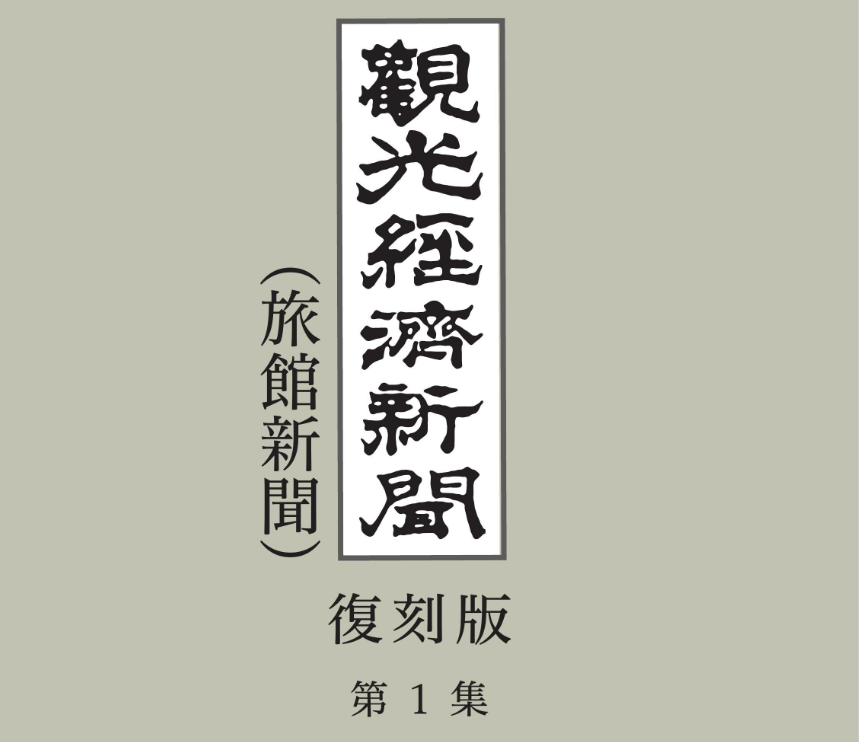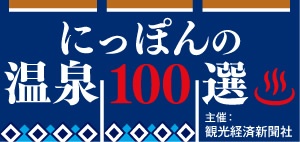内田氏
「情報収集と仮説設定」
昨年の4月前後、情報収集に長けた旅館経営者はこのように考えたのではないだろうか? 「少なくとも1年は苦しい時期が続く」。
しかしながら1年を経過した今になっても状況の不透明さは増すばかりである。ワクチン接種の遅延や急激な亜種の出現などマイナスの変数効果が大きく、困難な状況はまだまだ続く。
昨年の初夏に発表された大手戦略コンサルのレポートでは、コロナ以前に戻るには最短で4年、最長で7年との見通しだった。当時はその結論に若干懐疑的だったが、今になっては納得している。やはりコロナは一筋縄ではいかない。
弊社ではリスク分散のためポートフォリオの見直しを昨年から開始。旅館に続く新業態として和栗モンブラン専門店を3月に地元に開業した。テイクアウトも重視した店舗設計になっており、初年度から旅館本体比較で15~20%程度の売り上げ規模を見込む。宿泊自粛下でも地元客や至近の住民需要を取り込め、かつ宿泊トレンドとは異なった動きをすることから、大きなヘッジ効果を感じている。
また、顧客の感染リスク回避意向が事前想定よりもはるかに強いため、5カ年計画で進めていた「全室露天風呂付き客室化計画」を前倒しで実行する。まず今年5月より離れ棟の4部屋を露天付き化して付加価値を高める。これで客室全体の約半分が露天風呂付き客室となる。
旅館の場合、資金確保問題はイコールで金融機関との折衝問題となるはずだ。私は以前に都市銀行に勤めていたこともあり、金融機関との信頼関係がいかに重要であるかを扉の表と裏から見てきた。担保余力があるなら、その余力をどこまで、どんな事業に活用するのか。担保余力がない場合は、いかに実現可能で詳細な、説得力のある資料を作れるのか。そして、それを機関に対しトップの言葉で語れるのか。こういった地道な努力と関係の構築が「まさか」の事態に効果を発揮する。
不透明な時代に旅館の経営者がもっともすべき仕事は「情報収集と仮説設定」であると考える。3カ月後にどうなるのか、半年後にどうなるのか、1年後は、3年後は。責任ある見通しを立てることができるのは経営者本人とごく限られた役員だけだ。さまざまな情報をあらゆる方法で収集し加工し、仮説を立てる。そして実行する。苦しいが、その繰り返ししかない。
本日(5月6日)は米国の株価がかなり上昇した。ワクチン接種進行により先行きの経済見通しが明るくなったからだという。予測より長期化はしているものの、永久に最悪期が続くわけでもない。来るべき回復期に向けて、下を向かずに前を向き歩いていくべきだと思う。その時に必要なのは業界の仲間だ。時には酒でも酌み交わしながら励まし合っていくことが大切である。困難な時期の経営は自身のメンタルとの戦いでもあるからだ。